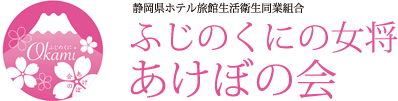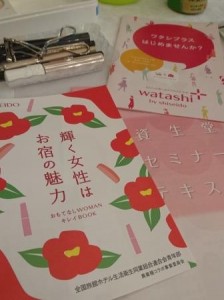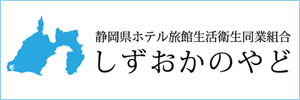Author Archive
新年研修会開催について
新年研修会の日程等をお知らせいたします。
記
日 時: 平成29年2月8日(水)10:15受付開始 11:00講演開始
会 場: 掛川城 竹の丸(http://kakegawajo.com/take/)
掛川市掛川1138-24 (掛川城二の丸ではありませんのでご注意ください)
*懇親会はバスにて移動後、掛川グランドホテルにて開催
研修講演会: 講師 小和田 哲男氏 (静岡大学名誉教授)
演題 「井伊直虎と家康」
平成29年のNHK大河ドラマでもある 井伊直虎 を題材に、ドラマで時代考証をされる
小和田先生のご講演となります。
皆様、お誘いあわせの上ご参加くださいませ。(詳細等ご案内通知は、年明けとなります)
なお、会場の掛川城竹の丸は建物の構造上、冷えますので防寒対策と
スリッパ等の履物をご持参くださいませ
静岡ホテル旅館生活衛生同業組合 事務局
中部地区おもてなし研修会で美しく!
師走の慌ただしい中ですが、女将さんは凛と美しく!と
身だしなみには、いつでも余念がありません。
今回の中部地区のおもてなし研修会(12/15)では、資生堂さんを講師にお迎えし
「おもてなしヘア&メーキャップ」セミナーを開催いたしました。
セミナーは、平成26・27年に資生堂さんと全旅連青年部の異業種コラボ事業委員会との
コラボによる、旅館やホテルで働く女性を対象に考案しているセミナーです。
「イキイキメーキャップ」と、「メリハリメーキャップ」というご提案。
朝など、お客様にさわやかな印象を与えたい<イキイキメーキャップ>、
午後、お客様を華やかに女性らしい印象でお出迎えしたい<メリハリメーキャップ>
そんな、おもてなしの心を伝えるための印象づくりをお勉強いたしました。
今、富士山が一番美しく見られる季節に、笑顔で皆様をお出迎えさせていただきます。
是非、静岡県にお泊りにいらしてくださいませ。
ふじのくに静岡 ホテル旅館 女将 あけぼの会 事務局
災害時、「女将のおもてなし袋」を実現化に向けて検討中!
かねてより災害時のおもてなしを検討している、あけぼの会では、
今年度「女将の地震初動マニュアル」をさらに進化させる。
具体化するための分科会を立ち上げました。
地震防災のおもてなしとして、「女将の地震初動マニュアル」で、有事がおこった際に、お引止め
するのか、お発ちいただくのか・・・どういう場合であってもやれるだけのことはしよう。と、
実際にやれることに限度はあります。でも、おもてなしのこころは同じですから、できるおもてなしを
模索いたします。
お発ちいただく場合も、お引止めする場合にも、女将のおもてなしの心を、形にしたいと考えています。
それが、「女将のおもてなし袋」の提案です。
分科会① 平成28年10月13日
代表者による分科会を立ち上げました。
おもてなし袋の、名称や形状、中に入れる防災用品の洗い出しから始めました。
2回のワークショップで感じたことを、取り込んでいきます。
そこに加えるのは、~女将らしさ~ 一番大切なことです。
あけぼの会会員向けアンケート実施
中・西伊豆地区 意見交換会を開催
分科会② 平成28年11月30日
あけぼの会会員施設をはじめ、静岡県の施設に波及させるため、コストやコスト以上のアイディアを
盛り込み付加価値をつけることを目指します。
できる限りの会員意見を盛り込み、気持ちを一つにして、おもてなし袋を完成させます。
お披露目は、あけぼの会 新年研修会<平成29年2月8日於:掛川市 掛川城 竹之丸>にて
行う予定で、急ピッチに進めています。
富士山、信仰と宗教の山
富士山は、富士山そのものを神さまとしたり、信仰・崇拝の対象とする信仰の山です。代表は、浅間信仰で各地に浅間神社があります。その他、著名なものに富士講や村山修験などがあげられます。
富士講は、江戸時代、御師が宿舎の提供だけでなく、教義の指導や祈祷など富士信仰全般を世話し、これによって庶民の間で爆発的な興隆を見せました。関東・中部はもちろん、東北や近畿など全国的に広がり、これによって各地に浅間神社が祀られ、富士塚が築かれるようになりました。
一方の村山修験は、富士山頂に大日寺を構えた末代上人が山麓の村山(現富士宮市)の富士山興法寺を拠点に行った富士山域の回峰行です。富士講に比べ修行色が強く、富士山腹から宝永山や愛鷹山、三島明神(三島大社)などを26日かけて巡ったと言います。
全日本大学女子選抜駅伝競走は、名前の通り日本学生陸上競技連合主催の女子の大学駅伝大会です。平成6年から開催され、平成25年からは正式略称を「富士山女子駅伝」として、富士山本宮浅間大社前をスタートし、富士総合運動公園陸上競技場までの7区間全43.4kmのコースで、例年冬季に行われてきました。富士での開催4回目を迎えた今年は、年末12月30日の開催となっています。さしづめ、現代版の回峰行と言えるのでしょうか。
浅間信仰の核となる浅間神社は、静岡県や山梨県を中心に全国に約1300社が分布しており、静岡県では115社が数えられます。富士山8合目以上の大半を境内とする富士山本宮浅間大社(富士宮市)を総本宮としています。
ちなみに、富士山頂を含むこのエリアは、県境をめぐって静岡県と山梨県の間に争いがあり、どちらの県でもありません。山頂の神社や富士山頂郵便局の住所は、「〒418-0011 静岡県富士宮市粟倉地先」。県境がないのも、県境が定まっていないのに住所が静岡県というのも不思議です。
タイトルの「富士山、信仰と宗教の山」の意味は、富士山そのものを信仰の対象とする宗教活動もそうですが、神々しい富士山の周辺にはその他数多くの宗教的な遺産が残されています。富士山には月見草ならぬ新旧取り合わせて宗教が似合うのです。
古くなりますが、日蓮上人は1257年富士市岩本にある実相寺に籠り、天台宗僧・円珍が唐から請来した一切経を閲読、思索し、同寺で立正安国論を起草しました。政治、宗教のあるべき姿を当時の鎌倉幕府執権北条時頼に提出したものです。残念なことに、その一切経は、一部を残して武田氏の兵火により焼失しています。実相寺は、富士市でも有数の伽藍を備えたお寺であり、その佇まいは日蓮聖人ゆかりの寺として整備されています。
富士市今井の毘沙門天は、お寺のHPによれば「今を去る千年余、山伏たちが寺裏の田子の浦海岸で水ごりを取り、海抜ゼロメートルから富士山に登った、その禊ぎの道場が当山の起こり」とされています。このお寺を出発点に海抜ゼロメートルからの富士登山もありかもしれません。
主神の毘沙門天像は、聖徳太子の御親作と伝わっています。普通の像が悪鬼を踏みつけているのに対し、この像は聖徳太子の上に毘沙門天王が立って護るという開運の「守護神像」だそうです。『日本書紀』第21には、聖徳太子が物部守屋を征討した時、四天王像を造って祈願して戦勝し、後に摂津国に四天王寺を造立した、と記されています。聖徳太子と四天王、なかでも毘沙門天とのかかわりは深い関係があります。
富士の毘沙門様は、正式には香久(こうきゅう)山妙法寺といいますが、これも奈良の香具山にちなんだ名前との説もあります。伝説では、聖徳太子が神馬に乗り、富士山を越え、信濃の国に至ったとする「甲斐の黒駒」伝説もあるなど、静岡県の富士から山梨県、長野県にかけては、聖徳太子と強いつながりのある地域です。
なお、この毘沙門天の2月の大祭は、日本三大だるま市の1つとして有名で、ここで売られる立派なひげのだるまは五穀豊穣、商売繁昌などの縁起物として人気があります。
このほかにも、沼津の白隠禅寺、興津の清見寺など、富士を取り巻く名刹・古刹が数多くあります。富士山と信仰をテーマに行脚する旅はいかがでしょうか?
静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 専務理事 府川博明
静岡県紅葉情報2016
(写真は2015修善寺)
秋の深まりとともに、木々の装いも彩豊かに変化していき、
だんだんと静岡県内でも紅葉が見ごろを迎えます。
(写真は2014年修善寺)
紅葉情報は下記をご参考に。
紅葉情報 日本気象協会
雪化粧をした 富士山 、夕日、・・・そして静岡の美味しいもの
とともにお楽しみください。
是非 i静岡県にお泊りにいらしてください。
ふじのくにしずおか ホテル旅館 女将 あけぼの会組合事務局
富士山と「大生部多」の話
今から約1370年の昔、日本書紀第24巻の皇極記にでてくる富士山麓に住んでいた大生部多(おおふべのおお)の少し変わったお話を紹介したいと思います。
原文は、漢文でとても読みにくいので、やや正確さを欠くかもしれませんが意訳すると次のとおりです。
東国の不尽河(富士川)のほとりに住む大生部多は、虫を祀(まつ)ることを村里の人に勧めて言いました。「これは常世(とこよ)の国の神。この神を祀るものは富と長寿が得られる」。男女の神官たちも、人々を欺いて神の言葉に託して「常世の神を祀れば、貧しい人は富を得て、老いた人は若返る」と人々に家の財宝を捨てさせた。人々は酒や野菜、家畜の肉を道ばたに並べ、「新しい富が入って来た」と浮かれていました。
都の人も田舎の人も、常世の虫を取って、清らかな場所において、歌ったり踊ったり、珍しい宝を棄捨しました。それで得られるものがあるわけもなく、損失が多くなるばかりでしたので、山城国葛野郡(現在の京都市右京区あたり)の秦造河勝(はたのみやつこかわかつ)は人々が惑わされているのを憎んで、大生部多を打ちこらしました。神官たちも恐れて、祀ることを止めました。その当時の人は次のような歌を歌いました。「太秦(秦造河勝)は 神のなかの神と聞える 常世の神を 打ちこらしたのさ」
この常世の虫は、橘や山椒に付く長さ四寸、大きさは親指ほど、色は緑色に黒い斑点があって、形は蚕に似ている。
以上が日本書紀に記された物語です。この話の中に出てくる「常世の虫」は、柑橘類につくアゲハチョウの幼虫ではないかと言われています。「常世の国」は、古代日本で信仰された、海の彼方にあるとされる一種の理想郷で不老不死や若返りなどと結び付けられ、同じく「日本書紀」の垂仁紀では、垂仁天皇が田道間守(たじまもり)を常世国に遣わして、不老不死の薬となる「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」を求めさせたが、その間に天皇は崩御したという記述があります。
この時、常世国に求めた木の実が「今橘と謂ふは是なり」とあって、この時代には橘(以下表記を「タチバナ」とする)のことと考えられていました。
静岡県史には、現在の富士市の田子の浦港と浮島沼の一帯は、富士の広大な裾野に加えて、駿河湾と富士川、浮島沼などの沼沢地があってさまざまな自然の産物をもたらす聖徳太子とゆかりのある「稚贄屯倉(わかにえみやけ」、全国におかれた皇室の直轄地のひとつであったといいます。
ここから先は想像です。大生部多は、タチバナが常世の国からもたらされ、それに付いて来たアゲハチョウの幼虫を常世の国から来た神と認識したこと。もう一つ想像をたくましくすると、すでに静岡県の富士川のほとりはタチバナをはじめ柑橘類の植物が栽培され、大生部多もそれに携わっていたのではないかと思われます。
当時は、現在の静岡県はもちろん、神奈川県から茨城県まで広いエリアでタチバナが栽培されていたことは、現在に残る地名や風土記などから推測されています。今も、駿河湾に面し、温暖な気候に育まれた沼津市西浦地区は西浦みかんのブランドで有名ですし、戸田には国内最北限のタチバナの自生地がありますが、その当時の名残ではないかと思われたりします。
この話の中に突如出てくる秦の河勝は、聖徳太子から仏像をもらって京都の太秦の広隆寺にお祭りしたという歴史上著名な、聖徳太子にゆかりの深い人物です。
この大生部多が「常世の虫」を祭る事件を起こしたのが西暦644年。前年には、聖徳太子の子供である山背大兄王子が蘇我氏の軍勢に責められ自殺しています。
そして、翌645年は中大兄皇子と中臣鎌足が中心となって蘇我氏を滅ぼした歴史でおなじみの乙巳の変(いっしのへん)、その後の大化の改新へとつながっていて、日本書紀に記されているこのエピソードも、何かそのあたりと係わりがあったような気がしてなりません。
このような流れの下で、この宗教事件を考えると、大生部多が蘇我氏に山背大兄皇子を殺されて手をこまねいている秦河勝に対するあてつけと考えると得心が行く部分があります。芋虫を祭ったのは、秦氏の絹生産の「蚕」を揶揄するもの、常世の国信仰も聖徳太子から仏像を与えられ広隆寺を興している秦氏の「仏教」信仰に対する挑発、聖徳太子ゆかりの屯倉の人々は、山背大兄王子を失い、一時的に無主の民に近い環境にいたのではないか、などなどさまざまに妄想がわいてやみません。ちなみに、大生部多の事件を鎮圧したとされる秦河勝は、現静岡県知事川勝知事のご先祖様で、秦河(川)勝の御子孫は秦氏と川勝氏に分かれたとのことです。昔から静岡県との縁が深いと歴史の妙に驚かされます。
静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 専務理事 府川博明
自転車を載せて路線バスで天城峠、河津へ
自転車を載せる棚「サイクルラック」を取り付けた路線バスの運行が九日から、
東海バス天城線の湯ケ島(伊豆市)-踊り子温泉会館(河津町)間で始まりました。
自転車の積載は、湯ケ島-踊り子温泉会館間のバス停十二カ所で無料で利用可能。
ラックはバスの前方に設置し、二台まで運べます。
運行ダイヤの問い合わせは、新東海バス〈電0558(72)1841〉へ
伊豆湯ヶ島 白壁荘 女将 宇田倭玖子
「ラブライブサンシャイン」の聖地巡礼って?!
沼津市・三津地区は、アニメ「ラブライブサンシャイン」の舞台となっていて
物語の舞台やモデルとなった地を巡る、”聖地巡礼”で賑わいつつあります。
そこで、三津旅館組合では、私どもの旅館を含めた7つの施設で 『パズルラリー』を
開催し(期間2016.10.15~2017.2.28)、コンプリート証明書を発行することになりました。
沼津・三津地区ではほかにも、電車やバス、フェリーでラブライブサンシャインの
ラッピングバージョンが登場していますよ。
美味しいお魚や、これからもっと美しくなる富士山をご覧に、 是非 お越しください。
沼津市三津浜 松濤館 女将 北野美和子
10.26初冠雪となりました
今朝は昨夜の雨のおかげで空気が澄んでいます。
とても富士山がきれい!
そして、昨日の寒さでやっと今朝、初冠雪を迎えました。
頭にちょこんとハンカチを載せたくらいでしょうか
風が吹いたら舞ってしまいそうな静岡県側の富士山です。
明日27日から、右の建物
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップにて
世界お茶まつり2016秋の祭典 が開催されます。
お茶にまつわる 音楽、香、花など様々なイベントが開催されます。
こちらは10.09の写真です
ふじのくに静岡 ホテル旅館 あけぼの会 事務局
食欲の秋は スイーツのまち藤枝 へ。
秋は、芸術、音楽、スポーツそしてやっぱり食欲の秋!ですよね。
(写真2枚は 真茶園さん)
(こちらは ななやさん)
茶処静岡県の中でも、有数の地域である藤枝市では、スイーツのまち藤枝 として
お茶製品だけでなく、地元素材や伝統・技が受け継がれるスイーツで町おこしをしています。
お店の近くまでいくと、お茶のいい香りがしてきます。
是非、おいしく楽しく街歩き をなさってみてはいかがですか?
ふじのくにしずおか ホテル旅館女将 あけぼの会 事務局